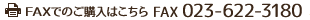今月のコラム
column我が道
山形もやっと冬が終った。今年の桜の開花は例年よりも早く4月12日頃だそうだ。去年の夏は冷夏で天然醸造をしているので、味噌の発酵が遅い。大豆や米の値段も上がっている。自然は自然で動いている。(人間がわるさをして迷惑をかけているのだが。)私は山形スローフード協会の一員である。またgooのスローライフ談話室の企画をしている。
とりインフルエンザそして六本木ヒルズの自動回転ドアの事故。グローバルスタンダード、勝ち組負け組、利益至上主義、効率の中現代人はとにかく忙しい。そして、一番忙しいのは「心」である。いつも、せきたてられる様に追いつめられる様に、心にゆとりややすらぎがない。「豊かな国、日本」もう少し考えてみた方がいい時期にきているのかもしれない。
私は昭和29年生れである。小学生の頃を思い出すとのんびりしていた。時間が過ぎるのが、とにかく遅かった。一生けんめい遊んだ。自然と一体化していた。ぜいたくはなかったが、それが不満にはならなかった。社会の現象を無視したり逃避したりできないが、私は「我が道」を行く事にした。今、50歳、あと何年生きているかわからない。社会風潮にふりまわされて、忙しくて死んで行くのはいやだ。生きていくのに同じ厳しさでも「自分の生き方・価値観」を中心に生きていこうと思っている。
PR
PRとかCMとか宣伝とか言われる広告。大企業はテレビやラジオ・新聞・雑誌でドンドン宣伝している。 大量生産をしているわけだから、大勢の人に買ってもらわなければならない。 そうすると、大量宣伝をしないと自社の製品を大勢の人にわかってもらう事ができない。
私は妻と二人で味噌を作っている零細である。生産量も少なく買ってもらいたいお客様の絶対数も小さい。 それでも、自分の商品を知ってもらわないと売れない事は、大小に関係ない。 昔は地域経済だったので、そこに住んで一生けんめい物づくりをしていれば、地域の人に知ってもらう事ができていた。
でも今は違う。地域の小売店がつぶれて、小さなスーパーも存在がむずかしくなりつつある。 流通が大きなスーパーに集約され、そこに納品するメーカーも、大手やそれなりの規模でないと取引ができなくなっている。 もはやこのままでは、小企業や零細・個人の規模は、成り立たない世の中になってしまう。 「良いものを作っていれば、必ず売れる。」と言われてきた。それは真実かもしれないが、実際はそうではない。 「良い物とか、何が良いのか」をお客様が知らなければ、そこに物があっても物の存在を知る事ができなければ、お客様は買えないのだ。 もはや、物作りだけではどうにもならない。 一生けんめい良い物を作って、その良さを何らかの方法でPRしていかないと、どうにもならないそんな時代である。
私の仕事
1月27日(火)午前11時~午後3時 東京都世田谷区のキャロットタワーにて、第3回語らいステージ『スローライフ・スローフード』~どうなってるの日本人の味覚~ が開催された。
多くの人が関わって、大変お世話になりました。語らいステージをやる意義を再確認する事ができました。
2月4日(水)検索サイトgooのスローライフコンテンツ内にある『スローライフ談話室』で今回の語らいステージの特集をやっております。動画4本もブロードバンドで配信しています。ぜひ見て下さい。また、スローライフ・スローフードの入門ビデオを自主制作しました。『スローライフ・スローフード』~同じ味じゃ、つまらない~(15分間テープ)です。gooショッピングもしくは直接私の所へお問い合わせ下さい。
私の仕事
新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
私の仕事は、妻と二人の小さな規模ですが、今年が底をつく時期になる様です。 自分が考えたみそ造りをしているため、売上げも利益も思う様にいかず、何でこんな事をしているのだろうと思いつつ自分の信念を貫いています。 別にお金もうけをして、ぜいたくな生活をしようとは思っておりません。昔からお金に縁がなかったので、気になりません。 でも家族の事を考えると、少しは良くなって欲しいと思っています。
1月27日(火)第3回語らいステージ「スローライフ・スローフード」~どうなってるの、日本人の味覚~があります。私はそこで言いたい事があります。 やれグローバルスタンダードとか勝ち組負け組とか誰が決めたかわからないルールにしばられ、リストラという言葉で人生をしばられ、 何を考える事もしゃべる事もなくなった日本人。何をしあわせと感じて生きていくのだろうか。人間は生きている限り、食べ続けなければいけない。 そのたべものだって、いざたべようと思うと似たりよったりの同じ味~味の均一化~である。 考える事も自己主張する事もなく、たべものはみんないっしょ、これではクローン人間になってしまう。
きびしい世の中だからこそ、たべものだけでも個性があっていいのではないか! 自分が生きている存在の証しとして、そして、たべものは生き物の生をたべているという感謝の気持ちの表現として、「自分の味」を持って欲しいと思う。 私のみそ造りは、様々な味の中の一つをつくっている大事な仕事と思っています。だから必死なのです。
語らいステージ
平成16年1月27日(火)午前11時より、東京都世田谷区三軒茶屋のキャロットタワーにて 第3回語らいステージ「スローライフ・スローフード」~どうなってるの、日本人の味覚~を開催する (定員制・有料・お問い合わせ TEL 023-622-4695 長谷川まで)。
11月25日(火)~28日(金)まで、幕張メッセにて、2003EFAFF第四回農林水産環境展に出展していた。 27日(木)夜7時から渋谷にて、コーディネーターをしてくださる伊庭みか子さんと打ち合わせをした。 結論も出ず、11時半になっていた。伊庭さんは、同時通訳者で翻訳家でもある国際通 の行動派の女性である。 日本で一番最初に遺伝子組み換え問題を提起した人である。
伊庭さんから「長谷川さん、何を言いたいのよ。何をしたいのよ。さっぱり、わからない。」と突っ込まれてしまった。 私は、あまり波風を立てず、まわりとの摩擦をおこさないで、とにかく、自分たちの考え方だけでも理解してもらおうと考えていた。 商売をしている私としては、ついそう考えてしまう。
伊庭さんは「ここに問題点があります。みなさん、これからこうしましょう。」と具体的に提言しないと、何も変わらず、 中味のないものになってしまうと考えているのかもしれない。 伊庭さんは、ながい間一生けんめいがんばってきた。海外でもそうだが、事なかれ主義の日本人に対しても「何をするのよ!」と訴えつづけてきた。 「何かを変えよう!」と思ったら、一歩前へ出なければいけないのかもしれない。
「かもしれない」なんて書いているとまた伊庭さんに言われそうだ。
本質
10月27日(土)秋田市で大学の校友会の東北支部長会議があった。
私は山形支部の一員(会計担当)として4名で参加した。大学の経営陣から、常務理事・校友会から副会長が秋田に来られた。 「これからの大学の卒業生の組織をどうするのか」という議題であった。東北にある各支部の支部長の長い意見が相次いだ。 次に講演を控えていたので、司会(秋田支部)の方が、全部おわらないうちに意見の集約に入ってしまった。 「せっかく遠くから来ているので、まだ残っている支部に発言させるべきだ。」との意見が出て、続行になった。
結果的には「雨降って、地固まる」という事になった。 たまたま講演者が卒業生だったので、予定の半分の時間になってしまったが、同じ仲間なので了解してくれた。 でも大変おもしろい話で、もっと聞きたかった。
10月28日(日)青森県に入った。私の無農薬みそのお米(無農薬無肥料栽培)を作ってくれている岩木町の木村秋則さんの所に行った。 青森県の米の作況指数が「71」と全国最低であり、太平洋側は「31」という状況であった。 木村さんのお米は強いので、どうにか大丈夫であった。
平成16年1月27日(火)東京の三軒茶屋にあるキャロットタワーで、 第3回語らいステージ スローライフ・スローフード「どうなってるの、日本人の味覚」を開催する。
料理の部と語らいの部に出席をお願いしている、弘前のフランス料理のシェフの方と夜、おいしい料理をごちそうになりながら話し合いをした。 木村さんと木村さんの仲間の農家の方が栽培している農作物を使ってレストランをされている。 木村さんからシェフの話を伺っていたので、前提の話はおわっていると思い、その先の話をしていた。
そうしたら、「どうして、私でなければならないのか。シェフが必要なら、東京の知り合いを紹介してあげます。」と言われた。 想像もしていな突然の質問に私はとまどってしまっていた。 (スローフードだからお願いをしていたのだが)説明に自分でとまどいながらも一生懸命話をして、理解していただいた。
大学の校友会の所では、組織が大きすぎ、すぐどうこうになるものでもない。主催県としては、スケジュールの問題もあった。 私の語らいステージの打ち合わせの件は、木村さんを通しての話であったので、私に甘えがあったのかもしれない。
共に「本質」のところで話が不充分であった。反省。
スローライフ談話室
第3回語らいステージ「スローライフ・スローフード」~どうなってるの、日本人の味覚~を 平成16年1月27日(火)東京都世田谷区三軒茶屋のキャロットタワーにて、午前11時より定員50名で開催する。 今回は日本全国の多くの人に私たちの思いを知ってもらおうと、インターネットのブロードバンド(TVムービー)に載せる事にした。 でも、サーバーの容量の問題が発生し、NTTグループ会社NTT-Xの検索サイトgooのgooスローライフにお世話になる事になった。 平成16年2月3日(火)よりブロードバンドで貼り付ける事になりました。
1分間のムービー4本で、1本は、語らいステージの風景、残り3本は、出演者の意見で、ノンフィクション作家 島村菜津さん、 無農薬無肥料りんご農家 木村秋則さん、フランス料理人 レストラン山崎の山崎 隆(たかし)さんです。 でも1分間というのはあまりにも短いので、パネリストの考えを文章にして読める様にした。 そんな中でgooさんより、私に「何か企画を出してくれませんか。」との話があり、11月4日(火)より、第1、第3火曜日、 そして平成16年2月より毎週火曜日更新で、「スローライフ談話室」が始まる事になった。
「スローライフ談話室」
http://slowlife.goo.ne.jp/danwa/
そして語らいステージ用のTVムービーの撮影に入った。 10月25日(土)26日(日)有機農業発祥の地・山形県高畠町に島村菜津さんがスローフードの行事で講師として来ていたので、 2日間TVカメラで追っかけた。 27日(月)28日(火)は青森県の弘前市で、レストラン山崎の山崎シェフ、岩木町のりんご畑で木村秋則さんを追っかけた。 私たちの庶民の催し物にしては、本格的なTVカメラの撮影であった。(もちろん、私が撮影したのではない。プロである。) この4日間撮影した映像を編集して「スローライフ・スローフード」としてビデオカセットにて有料にて頒布したいと思っている。 平成16年1月下旬の予定です。
社会への関心
8月末、残暑お見舞申し上げますと書かなければいけない時季なのだが、今年は夏は来なかった。 低温と長雨そして日照不足で農作物が大変である。
私は仕事柄、常に気象を気にしながら、北海道・青森・山形・県内の契約栽培農家と常に連絡を取っていた。 気象が変だなぁとは、去年の冬からずっと思っていたが、ここまでひどくなるとは考えられなかった。 農業技術がいくらすすんでも、自然には勝てない。工業製品の様に農作物が毎年安定して出てくるとはかぎらない。
ところで、国の来年度の予算編成の件でテレビニュースで「財政破綻が目の前に迫っているなかで、来年度の予算編成が...」 という言葉があった。 簡単な話が、40兆円の税収と40兆円の国債という名の借金で、 家庭におきかえると、年収400万円の家で400万円の借金をして、800万円の生活をするのと同じ事だと言っていた。 「国の財政破綻」テレビのニュースで言われると、のほほんとしていられる状況ではないのかもしれない。
自分の事だけを考えて、社会の問題に無関心で生きてきた日本人
人間の欲望に合わせて、世の中を作り上げてきた日本人
でもこれからは、自分や家族を守る事すら大変な世の中になりそうなので、 他力本願ではなく、自力で自分や家族を守る覚悟が必要になっていくのかもしれない。 そのためにも、社会や世の中に対して無関心であってはならない。
宝くじ
8月1日 朝5時より北海道の無農薬黒大豆の無農薬黒大豆みそを造っている。やっと今日でみそ煮がおわる。 朝から晴れて、夏が到来した。さわやかな気持ちである。1ケ月ちょっとみそ煮はお休みである。4月からのエンドレスの仕事が一区切ついた。 今回も本当に疲れた。
7月、東京で無農薬みそを販売していただいている流通のある店舗の担当者から、電話があった。 近くまで行くので「ぜひ工場を見せて欲しい」と。私は言った。 「従業員もいない規模である。工場などではありません。仕事場とか作業場とかならあります」と。 近代工場とは正反対の光景で、カルチャーショックを受けて帰ってしまうのが常なのである。
山形に来られて、いろいろと説明やら話やらをした。 一言、「大変だねぇ。」そして「長谷川さん、みんなこれに戻りたいんではないのかなぁ。」と。 大変造詣の深い方で、ありがたい言葉であった。
でも、長時間重労働で、しかも効率が悪く、お金にも縁がない。だから、機械化し、効率を求めてきた。 きつい肉体労働に戻るのは、大変だと思う。みんながみんなお金がもうかったら、いいのだが。 自由に競争して、能力のある人が富を得る。平等にチャンスがある。アメリカ式グローバルスタンダード。
実際に富を得るのは、数%である。宝くじなのだ。宝くじを買うと3億円あたる。 海外旅行に行こう。やれ、家を買おう。私なら借金がかえせる。残ったら貯金しよう。 何人に3億円が当たるのですか。私なんか宝くじを買わないので、可能性0である。 宝くじ1枚買って1枚当たっても、3億円にはならない。300円を連番で10枚買う。 10枚買う人もいれば、100枚、1000枚、10000枚買う人もいる。宝くじだって平等ではないのだ。
生き方、考え方、価値観が多様でいろいろあった方がいい。3億円を夢みて、散財して、ごくごく一部の人たちがもうかる宝くじ。 グローバルスタンダードとは、たとえ話でいうと、こんなものだ。 「楽して、何かいい事があるかなぁ。」と考える。そんな時代はない。 そろそろ眼を覚ました方がよいようだ。
仕込味噌
私は、今、昔から続いている地元の仕込味噌を造っている。仕込みとは、原材料を混合し、容器に入れる事である。 味噌で言えば、大豆を煮て、切って、米をふかして麹にして、塩と混ぜて、桶に入れるという事になる。 この段階では、発酵していないので、みそとは言えない。毎日、朝4時半に希少するが、ねむくてしかたない。 やっと5時に仕事場に入り、最初におかま個を洗って、水を張り、火を入れる仕事から始まる。 午後3時40分頃おわり、4時から6時半まで、市内の各家庭に配達し、夜の6時半から8時まで、次の日の仕込みの準備をしている。
出張以外は毎日のこの連続となり、疲れ果てて、左手をやけどしてしまった。 米をふかす作業で、お釜の熱風でやってしまった。数年前も、お釜のお湯をバケツに入れ、何と、そのお湯に右手をつっこんでしまった。 全く必要のない作業である。疲れると、頭の脳の回路がおかしくなるのかもしれない。 手づくりとは長時間のきつい肉体労働である。
この仕込み味噌が年々、生産量が減っていく。当方も、特みそ・特々みそ・無農薬みそ等の製品味噌が仕込味噌よりも多くなっている。 仕込味噌は手づくりみそであり、日本の食文化としても、みその文化としても大切なものだが、父や母の時に比べると生産量 が半分になってしまった。 たぶん、このままでいくと、5年後はさらに今の半分になっているだろう。 お客様が高齢化し、亡くなったり、家族の人数が減ったり、次の若い世代に引き継ぎができなかったり、また、1年分のみそを造って、 1年分のみその代金を払うのも一因だったりする。 製品味噌専門メーカーならいいが、私の様な代々の麹屋さん兼みそ屋さんをやっていく者が日本中で廃業をしていくと、 日本の手づくりみその文化も消えてしまう。 私は、長谷川の山形仕込味噌として、たとえ少量 になっても、仕込味噌の文化を守っていきたい。 この火を消したくない。
カテゴリー
新着情報
- 2026.02.01
- 寒い、寒い、寒い、
- 2026.01.01
- 新年おめでとうございます
- 2025.12.02
- 師走となりました
- 2025.11.01
- 有機JAS認証の検査がありました。
- 2025.10.21
- コラムが遅れました
- 2025.09.02
- 暑いと、何でもいやになる
- 2025.08.02
- 雨が、やっと降った???
- 2025.07.04
- お米
- 2025.06.04
- 備蓄米
- 2025.05.05
- 年には勝てない。