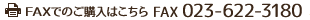今月のコラム
column「手造り黒豆みそ」仕込みはじめました。
「手造り黒豆みそ」は、7月2日(土)に米の浸漬をして、5日(火)に今年はじめての仕込みをしました。今月は,「手造り長谷川みそ」「手造り黒豆みそ」そして地元家庭用の「仕込味噌」を、暑い日々の中、毎日肉体労働をしていました。ヘトヘトに疲れました。
29日(金)に前半の仕込が終わり,8月下旬より後半の仕込をはじめます。これから束の間、からだの休息です。
30日(土),川崎から,長男夫婦ともうすぐ2歳の孫が,夏休みで遊びに来ています。31日(日)、長男夫婦のリクエストで,松尾芭蕉が『奥の細道』で「閑さや岩にしみ入蝉の声」という俳句を詠んだ山寺・立石寺に妻とともに行ってきました。
山寺へは何度も行っていますが,妻も私も仕事の疲れがひどく,奥の院までの石段の3分の1位のところにある芭蕉の供養碑「せみ塚」の休憩所で、休みをとりました。長男夫婦と孫は、元気いっぱい登っていきました。私どもは,その姿を見送り,待つことにしました。
いつも石段を登るのが精一杯で,ゆっくり周りを見る余裕がありませんでした。休みながらながめると、石段の脇に大きな岩をまたいで杉の木がそびえ立っていて、岩壁の割れ目にはしっかり木が生えています。すごい生命力です。
私も,自然の生命力に負けない様,がんばっていきます。
3・11以降(3)
「手造り長谷川みそ」の今年最初の仕込みは、6月17日(金)に米の浸漬をし、6月20日(月)から始めました。例年より2ケ月遅れています。「手造り黒豆みそ」の最初の仕込みは7月の予定です。
山形県は、県名でもわかる様に、山だらけです。日本海側の秋田県境にある鳥海山(2,236m)。庄内地方にある山岳信仰で有名な月山(1,984m)。新潟県福島県境の飯豊連峰(飯豊山 2,105m)。東北地方の中央を走っている奥羽山脈があり、福島県境にある吾妻連峰(西吾妻山 2,035m)、宮城県境には奥羽山脈の一部・蔵王連峰(熊野岳 1,841m)と高い山々が要害の様にそびえた立っています。
6月22日(水)の毎日新聞山形版の記事によると、東日本大震災で、私が住んでいる山形盆地の震度が、奥羽山脈を隔てた太平洋側に比べて小さかったのは、山脈の地下(20~60km)に横たわるといわれる柔らかい岩石が地震の揺れの横波(S波)を通りにくくし、山形盆地に届く前に揺れが弱くなったと、山形大学の川辺孝幸教授(災害地質学)が、21日発表したと書いてありました。奥羽山脈のおかげである。どこに行くにも、山々を越えなければならず、大変な思いをしてきますが、今回はその山々に助けてもらいました。
3・11以降(2)
私のみそ造りは「天然醸造」なので、11月から3月までは、山形は寒くて、みそは発酵しませんので、仕込みは休んでいます。
今年は、代々やっている地元家庭のおけでねかす仕込味噌のための麹をつくるために、4月19日(火)米の浸漬をし、4月22日(金)から仕込みをはじめました。製品みその仕込みの合間をぬって、7月までやっています。
山形の生協さんや学校生協さん、そして、銀座にある山形県のアンテナショップ「おいしい山形」でも取扱いしていただいている製品みそ「手造り特みそ」は、5月28日(土)に米を浸漬をし、5月31日(火)より仕込みを始めました。今日も「手造り特みそ」の仕込みをしています。今年のみその仕込みは、3月11日の東日本大震災の影響なども考慮して、仕込みの時期を決めています。
首都圏を中心に、日本全国で販売している「手造り長谷川みそ」「手造り黒豆みそ」の仕込みは、例年より随分遅れてしまい、大震災発生より3カ月経過する頃より始める予定です。
皆様においしいみそをお届けできるよう、今年も一生懸命励んでいます。
3・11以降(1)
3月11日の東日本大震災以降、どうも涙腺が弱くなったのか、震災のテレビを見るたびに、自然と涙が出てきます。
ゴールデンウィークですが、私は明治屋広尾ストアー(4月29日~5月1日)、紀ノ国屋インターナショナル[青山](5月3日~5日)、紀ノ国屋渋谷店[東急本店地下](5月7・8日)に、今回の大地震に際してご心配いただいたお礼をこめて、元気な姿をみてほしいと思い、売り場に立っています。
去年のゴールデンウィークは「手造り長谷川みそ」の仕込みをしていました。仕込みの始まりが、春の寒さで例年より遅れました。そして、夏は猛暑となってしまい、お客様には、ご迷惑をおかけしました。また、北海道では、長雨と猛暑の影響で、「手造り長谷川みそ」「手造り黒豆みそ」の原料の大豆が虫の害を多く受け、収穫量が3割減ってしまいました(以前、一度、冷害で2割減の時がありました)。
みその仕込み期間中は、ほとんど山形にいて肉体労働をしていますが、今年は少々時間が出来たので、東京に出て来ました。
大震災のテレビ報道、福島第一原発事故関連のニュースの中で、牛や豚、犬や猫が野原や道路をさまよっているのを見るにつけ、生きものは、人間を含めて、ほかの生きものの命をいただいて生きています。もっと真摯に自然に向き合っていかなければならないとつくづく思い知らされています。
東日本大震災(2011.3.11)
この度の東日本大震災におきまして、被災された地域の皆様に対し、心よりお見舞い申し上げます。
また、多くの方々から電話・FAX・お手紙で、私どもに「大丈夫でしたか」とのご心配をいただき、ありがとうございました。一時、宅急便が止まり、出荷できませんでしたが、おかげ様で、無事営業をしております。
M9の今回の大地震で、たくさんの方が亡くなられ、家を失いました。また、福島原子力発電所の被災により、放射能の問題が発生しました。誰もが想像だにできなかった事態です。被災された方々の早くの復興と原発問題の早期の収束を願うばかりです。
私は、おいしいみそ、いいみそを造ろうと、素材にこだわり、造りにこだわり、約1年から2年の間の期間での熟成にもこだわってきました。でも、自然・環境・社会・経済の安定なしに、本当の意味での物づくりはできないのだと改めて、つくづく感じています。
私は、天然醸造をしていますので、11月から3月まで気温が低くて、みそが発酵しませんので、みそ造りはしておりません。その間は、みその出荷と、主に東京でのみそのPRをしています。4月に入りましたが、今回の大地震の混乱で、みその仕込みの準備がこれからになります。今年は例年より遅れます。
[お知らせ]
東日本大震災の関連で、計画停電の地域にお住まいのお客様にお知らせ申し上げます。
私のみその保存方法は、冷蔵庫(0℃~10℃)で保存と表示していますが、みそは、塩分を含む、日本の昔からの伝統的保存食です。冷蔵庫内で十分にみそは冷えていますので、計画停電等では、特に問題は発生しません。いつもの様に冷蔵庫に入れて、おいしく召し上がってください。
時間がかかる
1996年設立した「食の学校」(代表塩川恭子氏)の15周年&第10回会員大会が、2月22日(火)、会場を銀座ブロッサムで開催された。ゲストスピーカーとして、青森の木村秋則さんがやってくるという事で、塩川先生から、「木村さんと久しぶりにゆっくり話をしたら」と、案内状を送って頂きました。
「食の学校」が目指した事は、自然環境を大切にし、自然に寄り添った農産・水産・畜産の支援と普及、日本の食文化や伝統的製法食品・自然食品の次世代への継承、おいしくて安全な食べ物を食卓に届けるための生産者・メーカー・流通・消費者の顔が見える想いの通じるネットワークづくりでした。塩川先生は、40年間、食の問題に取り組み、「食の学校」を初めて15年、いろいろな事があったようですが、今も変わらず真剣に向き合っています。
大会が終わり、築地で懇親会が行われました(写真 左:塩川氏、中:木村氏、右:私)。懇親会も終わり、木村さんと私は7時30分にはホテルに戻りました。木村さんは、自然栽培の普及のため、国内外での栽培指導・講演、本の執筆、テレビ出演などスケジュールがいっぱいで、本当にトコトン話をしたのは久しぶりでした。お互いの家族の事、自分の事、自然栽培の事、仕事の事、世界情勢の事など。時間を忘れて話をして、気がつけば、真夜中の2時でした。
私は木村さんに、「もう無理をしないで欲しい」と言ったら、木村さんは、「アハハハ、年だなあ、からだが言う事きかないよ」と。
塩川先生は40年、木村さんは30数年。ながい時間をかけて、志を貫いている。私も時間はかかるだろうが、私のテーマ「自然のおいしさ」をもとめて、がんばっていかなければと思う。
雪が多くて、大変です
朝、起きたらまず窓のカーテンを開く。
「ああ、今日もまた雪が積もっている。“雪はき”をしなくっちゃ」
真夜中に雪が降っているのは、寝ている時には気がつかない。雨が降っている時は、雨音がする。風が吹けば、風音がする。雪はしんしんと空から音もなく降ってくるのである。アダモの歌、『雪が降る』の世界である。“雪はき”は一時間近くかかる。今年は、とにかく雪が多い。テレビのローカルニュースは、知事が農業の大雪被害の視察であった。
私の味噌は、天然醸造なので、みその仕込み作業は冬は休みである。今は、紀ノ国屋さん・明治屋さんでのみそのPRのため、東京に行ったり、山形に戻ったりのくり返しである。
山形のたいていの人たちは、買い物は車で行く。雪が多いと買い物を控えてしまうが、東京の一月は寒くて、お客様の来店数も少なくなるようだ。
去年は猛暑で、今季の冬は雪と寒さ、いろいろ大変です。
三つのこだわりを守っていきます
新年あけましておめでとうございます。
旧年中は、皆々様に大変お世話になり、ありがとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
平成22年は、猛暑の年でした。農産物も水産物も大きな打撃を受けました。私達の味噌・醤油業界も大変な一年でした。猛暑のため、発酵が進み、色が例年よりついてしまい苦慮しました。自分ばかりが苦労しているのかと思っていたら、同業者の皆様も同様でした。
気候変動の激しい時代が予想されており、今までの製造方法を見直す所も増えていく様です。それでも、私は、私の三つのこだわり「無添加・手造り・天然醸造」を必死で守っていきたいと思います。
食+料=∞ (無限大)
11月17日(水)青森県弘前市で、弘前フランス料理研究会主催で、『食+料=∞ (無限大)』(農業者と料理人のコラボ、食で地域を元気にしよう)が開催されました。日本経済が低迷する中、地方はどうやって生きて行くのか。自然生態系を護りながら、正しい農業を営む農業者とその生産物を活かして料理を創造する料理人、お互いに理解し合い助け合うことにより、食を通して、地域経済の活性化につなげ、地方から発信し、日本を明るくしていこうという主旨で、弘前が誇る農業者と日本を代表するシェフが集まってきました。
農業者として、奇跡のリンゴを育み、日本から世界に自然栽培を広げる木村さん。木村さんから自然栽培を学びながら、野菜づくりに励む成田陽一さん。自家配合の発酵飼料で自然飼育の養豚、卵を生産する長谷川陽子さん。シェフは、フレンチのホテル・ドウ・ミクニのの三國清三シェフ。スローフード山形の仲間であるイタリア料理アル・ケッチャーノの奥田政行シェフ。函館のスペイン料理バスクの深谷宏治シェフはじめ、多くのシェフが参加しました。
午後3時半からシンポジュウム(司会:レストラン山崎 山崎隆シェフ)『農業と食:その熱い思いを語る』。そして、午後六時半よりディナー『こだわりの食材:シェフ達の逸品を食する』が開催されました。
私は、農業者・料理人・食べる人、三者の関係を密にし、お互いに理解し合い、地球環境と人のからだと心の健康を大事にしていかなければならないと強く感じました。
会終了後、二次、三次会とつづき、あけて18日(木)午前0時に向けてのカウントダウンが始まり、ボジョレヌーボー解禁で大いに盛りあがりました。
多くの人たちからいろいろな話を聞き勉強させていただきました。
舞台 りんご 木村秋則物語
11月4日(木)今年最後のみその仕込が終わり、夜、東京へ。5~7日まで明治屋玉川ストアにて、「手造り長谷川みそ」「手造り黒豆みそ」のPRをしていました。翌日の8日(月)ル・テアトル銀座にて、『舞台 りんご 木村秋則物語』を観劇しました。偶然にも、私の斜め前の席に木村さんがやって来ました。ビックリ! ハプニングという設定で、舞台あいさつのために来たそうです。
満席の中、V6の長野博さんが木村さん役で、木村さんの奥さん役に佐藤江梨子さんが演じました。木村さんが結婚してから、りんごの無農薬・無肥料・除草剤不使用に挑戦して、8年目にりんごの木の一本に花が7つ咲き、ゴルフボールぐらいのりんごが2個収穫するまでの、木村さんとご家族の苦闘人生が演じられました。木村さんは、見ながら涙を拭いていました。
終了し、帰ろうとした観客たちが、突然舞台に木村さんが登場し、全員総立ちになりました。木村さんのあいさつが終ると、木村さん役の長野さんが、「今日は、木村秋則さんの61歳のお誕生日です」と言って、全員で「ハッピバースデー」を唄いました。感動のフィナーレでした。
楽屋にお邪魔して、コーヒーを飲みながらの談話の中で、私が木村さんに、「今年は(猛暑なのに)木村さんのお米はいいねえ」と言ったら、木村さんは、「ハッセ(長谷川)、(猛暑みたいな時でも)自然栽培の俺の米はいいんだよ」と言った。冷害の時も強かった米である。
夜、劇場近くのとある場所で、「舞台 りんご 木村秋則物語 木村秋則さんのお誕生日を祝う会」が、舞台の出演者、スタッフ、関係者と、木村さんの仲間で、少人数でしたが、アットホームな雰囲気の中で行なわれました。私には初めての経験でした。
カテゴリー
新着情報
- 2026.02.01
- 寒い、寒い、寒い、
- 2026.01.01
- 新年おめでとうございます
- 2025.12.02
- 師走となりました
- 2025.11.01
- 有機JAS認証の検査がありました。
- 2025.10.21
- コラムが遅れました
- 2025.09.02
- 暑いと、何でもいやになる
- 2025.08.02
- 雨が、やっと降った???
- 2025.07.04
- お米
- 2025.06.04
- 備蓄米
- 2025.05.05
- 年には勝てない。